22
1. はじめに
みなさんは“ITバブル崩壊”という出来事をご存知でしょうか?
🐚「学校で習ったような……?」
🐚「経済的に良くなさそうな感じ」
🐚「そもそもバブルって何」
株式投資をしている方でも、実はよく知らないという方もいるのではないでしょうか。
私も投資を始めるまで、全く馴染みのない言葉でした。
ですが、投資関連の名著と呼ばれる本を読んでいると、必ずと言っていいほど出てくる言葉のひとつなのです。
「世界恐慌」
「ブラックマンデー」
「ITバブル崩壊」
「リーマン・ショック」
「コロナ・ショック」
これらのイベントは、まるでソシャゲのメインストーリーかのように共通認識として語られます。
ゴールド・ロジャーが処刑台にあがり、
四代目火影が九尾と戦い、
オスタニアとウェスタリスが冷戦状態であることを語るかのように。
>> いや、知らんのよ <<
そう思いつつ、そうも言っていられないためWebサイトやAIを頼り、調べたり考察を広げたりしながら読み進めています。
そんなとき、ふと気づいたのです。
『ITバブル崩壊って、グッズ収集と同じ構造では……?』
発売当時に高値で買い取った推しのグッズが、いつの間にか見る影もなく値下がりしている。
そんな悲しい光景を目の当たりにした経験のある人も、多いのではないでしょうか。
グッズを収集していると必ずと言っていいほど直面する現実です。
もやっとしながら、フリマアプリをそっと閉じたあなた。
ITバブル崩壊後の投資家たちも、同じ気持ちだったかもしれません。
今回は、私たちの身近な推し活文化“グッズ収集”を例に、歴史的大暴落である“ITバブル崩壊”という経済現象をわかりやすく解説していきます。
「ITバブル崩壊ってなんぞ?」
「推し活に大暴落と同じ構造が潜んでるって、何事?」
そんな推し活民の疑問を解消する内容となっております。
ぜひ、お付き合いいただけると嬉しいです。
2. ITバブル崩壊の3つのフェーズを「推し活」で解説
■1 1990年代後半/熱狂の始まり
【新ジャンルの登場】
[推し活]
とある漫画が某雑誌で連載を開始しました。
その斬新な世界観とストーリーはたくさんの人々を惹きつけ、ファンが急増します。
「このジャンルは絶対に大ヒットする!」
誰もがそう感じ、熱狂しました。
[ITバブル]
これは、インターネットという新しい技術が登場したときの世の中の声と重なります。
「これからはITの時代が来る!」
1990年代後半、人々はインターネットに無限の可能性を感じて熱狂していました。
【関連企業の急成長】
[推し活]
漫画がアニメ化され、映画が発表されると、たくさんの関連企業が参入してきます。
公式グッズが大量に販売されたり、コラボカフェが次々と開催されます。
あらゆる企業とのコラボイベントも発表され、漫画やアニメを観たことがない人にまで認知されるようになります。
さらには推し活専用の便利グッズ、ライブ配信アプリなど、版権と直接関係のないものまで雨後の筍のように増えていきます。
[ITバブル]
これは、当時IT業界に次々と現れたベンチャー企業(ドット・コム企業)とそっくりです。
【投資家の熱狂】
[推し活]
ファンは「今買わなければ後悔する」と感じ、グッズを大量に購入します。
「原作を読んでいないけど、SNSでみんなが買っているからとりあえずグッズを買っておこう」というライト層も出現し、ファンが雪だるま式に増えていきます。
さらに「転売すれば儲かるだろう」と転売目的のバイヤーも参入し、グッズの価格は定価を大きく上回り、フリマアプリなどで高値で取引されるようになります。
“作品への愛着”という実態を伴わない期待だけで価値が膨らんでいきます。
[ITバブル]
当時の投資家たちも、世の中の熱狂と過剰な期待に突き動かされるように、ドット・コム企業の株をどんどん購入しました。
株価は“実際の企業の収益”という実態を伴わないまま、ただひたすらに高騰し続けました。
これが、ITバブルの形成です。
■2 2000年代初頭/予兆「あれれ?おかしいぞ?」の瞬間
[推し活]
推しの人気が頂点に達し、ライブやグッズも一通り出尽くしました。
すると、ファンが冷静になり始めます。
「グッズ買いすぎたかも……」
「このイベント、思ったほど人が入っていないな……」
関連グッズが売れ残ったり、コラボカフェの空席が簡単に取れたりするようになります。
また再販やオンラインでの受注生産が発表されると、グッズの希少性が失われます。
そうして、フリマアプリに大量のグッズが出品されるようになります。
この時点で、“作品への愛着”ではなく“熱狂”によって膨らんでいたグッズの価値は失われます。
[ITバブル]
株価が頂点に達したとき、投資家たちも冷静さを取り戻しました。
いつの間にか、株価が“実際の企業の収益”を置き去りにして膨らんでいたことに気がついたのです。
企業の収益化が見込めないことが明らかになると、投資家は株を売却し始めます。
■3 2000年代初頭〜2002年/淘汰と生き残り
[推し活]
供給が増えたことでグッズの価格は急落し、買い手がつかなくなります。
すると、ブームに便乗して一時的に儲けようとした人々は市場から撤退します。
グッズの価格は落ち着き、本当に欲しい人が必要なものを手に入れられる状態になります。
本当に作品やキャラクターを愛する人々は、変わらずジャンルに残り続けます。
この段階で残る価値は、一時的な熱狂ではなく本質的な魅力に基づいたものとなります。
[ITバブル]
他の投資家の動きに気づいた投資家たちは、一斉に株を売り始めます。
すると、株価は期待で膨らんでいた分、一気に大暴落しました。
実力のない、ブームに便乗しただけの会社は資金繰りに行き詰まり、次々と倒れていったのです。
しかし、GoogleやApple社など、しっかりとしたビジネスモデルを持っていた企業とその株主は生き残りました。
この一連の出来事こそが、ITバブルの崩壊です。
3. グッズの価値は株と似ている
どちらも、新しいものへの期待が過剰に膨らみ、実態以上に価値が上がったら急落してしまうという共通点があります。
当然、企業はできるだけ長く熱狂が続くように努力します。
新しい要素を次々と追加してファンが離れていかないように努めたり、常に新規ファンを獲得できるように戦略を練っているのです。
そして、ITバブル崩壊を乗り越えて大きく成長した企業のように、長く愛されて市場で活躍できるジャンルをつくることを目指しています。
ちなみに、ジャンルそのものの衰退はなくとも、グッズひとつひとつに対する小さな暴落は常に起きています。
コラボカフェの開催初日と最終日にフリマアプリを開いてみてください。
熱狂によって膨らんだ株価の急落を体験できることでしょう。
コラボカフェや新しいグッズが発表されたときに感じるあのドキドキこそが、ちいさな熱狂なのです。
しかしそれは、ジャンルそのものの熱狂よりもさらに限定的な市場に留まります。
そのため、ジャンル全体で見るとささやかな出来事に過ぎないのです。
先日のトランプ関税ショックが、あっという間に回復したことをご存知でしょうか。
公式からの新情報によってジャンルの熱狂は瞬く間に復活します。
ただし株価と違い、一度値下がりしたグッズの価値が再び高騰することはほとんどありません。
ジャンルは常に新しい方向に進んでいきますが、グッズそのものが自ら価値を変えることはできないからです。
人間には同調効果という心理現象があり、多数派の意見や価値観に流されやすい傾向があります。
そのとき残っているのは、“作品への愛着”でしょうか。
それとも、“過去の熱狂”でしょうか。
4. まとめ:「推しは推せるときに推す」が鉄則
推し活は熱狂してこそ楽しめるものです。
そのエネルギーは推し活を楽しむ人たちの力となり、生活を豊かにしています。
それに、流行りに身を任せて熱狂を楽しむことだって悪いことではありません。
この夏、何の祭りかも知らずに浴衣で花火を観に行った人は大勢いるでしょう。
楽しそうな人たちの雰囲気に当てられて、よくわからないけど楽しかった──そんな素敵な想い出に文句をつける権利は誰にもありません。
でも、ある人はグッズを手放してからこう言います。
「お金と時間の無駄だった」
推しのために早起きをして並んだことや、
コラボカフェで可愛い写真を撮ったこと、
推しの誕生日に心をこめて祭壇を作ったこと、
現場で他のファンと交流したこと、
限定品のためにネットに張り付いて何時間も粘ったこと、
慣れないクレーンゲームに挑戦したこと、
推しを迎えられて嬉しかったこと。
そんな輝かしい日々を全てなかったことにして、肩を落とすのです。
グッズを手放すことを否定はしません。
私も手放しますし、価値観は変わっていくものです。
でも、心に傷を負ってしまうなら、投資で言うところの「リスクの取りすぎ」なのだと思います。
お金も時間も有限です。
その人は熱狂に身を任せて、リスクヘッジを怠ったのです。
未来のことを考えて立ち止まり、自分の選択を見直すことをしなかったのです。
グッズ収集が悪いわけでも、況してや推し活が悪いわけでもありません。
買わない後悔よりも買った後悔をしてしまいそうな人は、ぜひこの機会にご自身の推し活を見直してみましょう。
買うべきか、やめておくべきか。
その答えはあなたの心にしかないのです。
今回もお読みいただきありがとうございました。
ぜひまた遊びに来てくださいね。
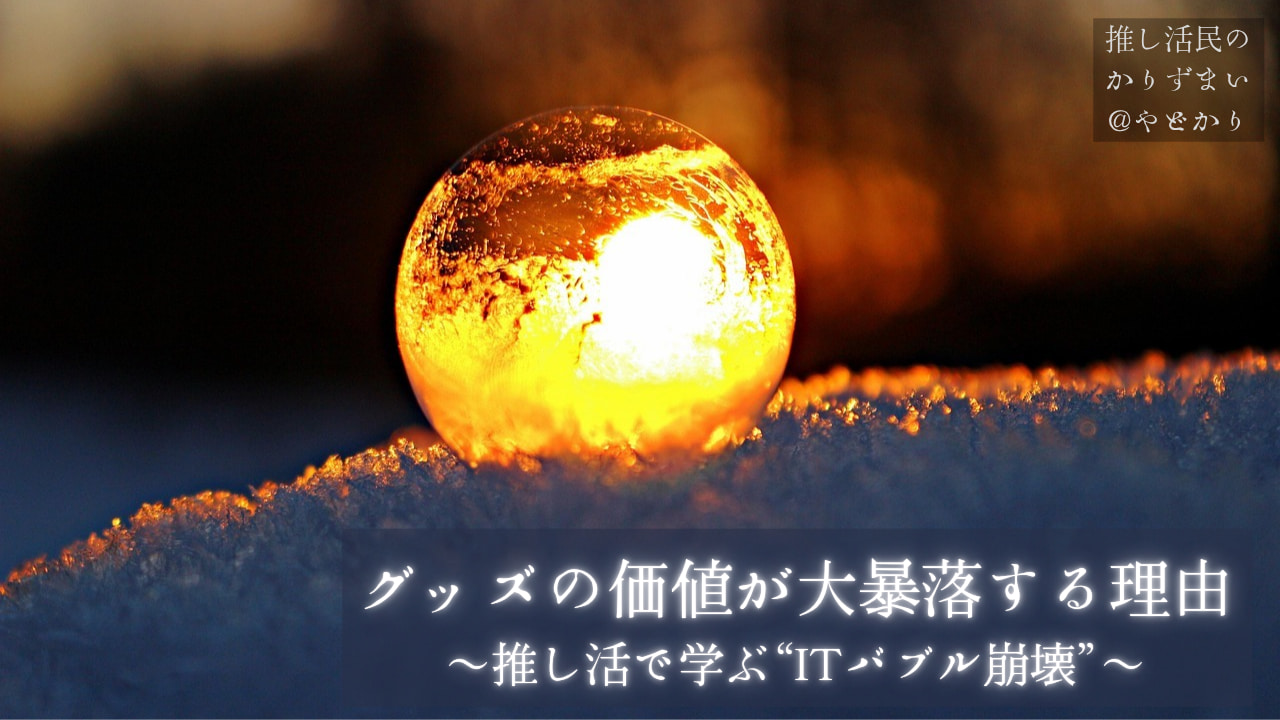


コメント